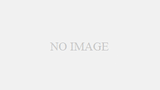みなさん、緑茶カテキンという言葉を聞いて、どんなことを思い浮かべますか。
実は、お茶が体にいい、と言われているのは、このカテキンという成分のおかげなんですね。
緑茶は紅茶やウーロン茶と違って、酸化されていないので、あの緑色が鮮やかで、そして、カテキンも特別です。
緑茶カテキンの抗酸化作用、そして、体への効果、死後に、緑茶の緑色を残したまま保存する方法について紹介しています。
お茶は身近な飲み物ですから、知っておいて損はない、そんなことがたくさんありますね。
お茶は世界中の多くの人に飲まれている

お茶は国際的飲み物
お茶は、ツバキ科に属している、中国南部に起源を持つチャノキという植物の新芽が原材料になります。
約4000年前には、中国皇帝によって緑茶の健康的可能性が記録されています。それ以来、お茶は薬用として利用されてきたんですね。
それから、お茶は嗜好性に優れているために、次第に生産地が広がって、現在では中国を始め、日本、インド、スリランカなどで栽培されています。
緑茶カテキンの持つ効果に注目
カテキンは、ポリフェノールの一種です。タンニンと呼ばれている、緑茶の渋みの主成分になります。
お茶のカテキンは、1929年に理化学研究所の辻村博士らが初めて存在が確認しました。また、カテキンは非常に酸化しやすく、お茶の性質も変化します。
緑茶は、荒茶の製造工程中で酸化酵素が抑えられるので、ほとんど酸化していません。そのために、お茶の色は元の緑のままです。
しかし、烏龍茶や紅茶では、酸化酵素の作用によって、酸化重合物といわれる合体カテキンができます。
それによって、本来は無色のカテキンが、オレンジから赤色へ変化するのです。烏龍茶や紅茶の色はそのためなんですね。
緑茶カテキンの効能
カテキンが生み出すはたらき
お茶の効能の多くはカテキンによるということが、最近の研究で次第に明らかにされてきたそうです。
いまでは、カテキンの効能として最も注目されているのが、 抗酸化作用と脂肪を燃焼する効果だといわれています。
良質な緑茶から抽出されたカテキンの抗酸化力はビタミンEの10倍、ビタミンCの80倍といわれています。
活性酸素は、免疫機能にとっては必要なものですが、過剰になると細胞や遺伝子を傷つけてしまうそうです。カテキンの抗酸化作用は過剰な活性酸素を還元してくれるのです。
さらに、カテキンのもつ殺菌作用は、細菌から身を守ってくれます。お茶でうがいをするのはそのためです。
カテキンが持つ血中脂質の減少効果は特に注目されています。これは緑茶の中に含まれるカテキンが強力な抗酸化物質だからです。
血中コレステロールの低下
緑茶を多く飲むと、血中コレステロール値が低くなります。これは、緑茶カテキンが、食事中のコレステロールの吸収を抑えるためだと考えられているのです。
血中コレステロールが高めの人にとって、緑茶カテキンは、悪玉といわれる「LDLコレステロール」を低下させ、善玉の「HDLコレステロール」は影響しないそうです。
体脂肪低下作用
カテキンは、食事とともに摂取すると、脂肪の吸収を穏やかにする特性をもっているといわれています。
緑茶カテキンが含まれるもの
抹茶のおいしさは、カテキンではない
お茶の葉の成長の具合や葉ができる場所によって、カテキンなどの成分の含有量は違ってきます。
ふつう、カテキンは、一番茶で約12~14%含まれています。そして、二番茶で約14~15%と増加するそうです。
そして、成熟した葉で先端から3~4枚目のものよりも、先端に近い、若い芽に多く含まれているようです。
玉露や抹茶に使われる碾茶=てんちゃのように光が当たらないような被覆栽培によって作られたお茶は、カテキンの生成が抑えられます。そのため、カテキンの量としては、煎茶よりも少なくなるそうです。
抹茶がおいしいのは、カテキンではなく、テアニンです。テアニンは、茶樹の根で作られ、葉の方に移っていくそうです。
しかし、テアニンに光が当たると分解してエチルアミンをつくって、さらにエチルアミンがカテキンに変化するそうです。
したがって、皮膜栽培された、玉露や碾茶は、光が当たらないのでテアニンが分解されず、テアニン含有量の多い、甘みのあるコクのあるお茶ができるのです。
緑茶カテキンの驚くべきはたらきとは
近年さらに注目されるカテキン
がんの予防
まず、注目すべきは、がんの予防にカテキンが役に立つという話です。これは、静岡県のがんの死亡率の調査結果から見つかりました。
緑茶生産地である静岡県は、がん標準化死亡比が男女とも全国値と比較して著しく低いことがわかったのです。
とくに、静岡県の中でも緑茶生産地である中川根町では、胃がんを発症する男性の割合が全国平均の約5分の1という調査結果が得られました。
また、他の調査で、直茶の飲む量が1日当たり、3杯以下、4~9杯、10杯以上で解析したところ、男性女性を問わず、緑茶を10杯以上飲む人はがんの発生率が4割以上低かったという調査結果が得られたそうです。
虫歯の予防
カテキンは、むし歯の原因菌であるミュータンス菌の増殖を抑え、プラーク形成も抑制するということがわかりました。そのため、虫歯予防に効果的だということです。
抗菌作用
カテキンは、大腸菌のO-157に対しても強い抗菌作用があり、赤痢菌・コレラ菌などの食中毒菌、さらにピロリ菌の増殖抑制作用もあることが明らかになってきているそうです。
抗ウイルス作用
お茶でうがいをするとインフルエンザ予防に有効だといわれています。ウイルス表面のトゲに、カテキンが吸着してウイルスの侵入を阻止していると考えられているそうです。